「中小企業診断士の資格を取るって決めたけど、独学と通学どっちがいいの?」
「中小企業診断士は独学だとどのくらいの勉強時間が必要なんだろう…」
「独学と通学で勉強時間に大きく差が出るなら、通学にしようかな…」
このように悩む方も多いでしょう。
ですが、勉強時間はその方の経験や勉強方法などに大きく左右される、というのが事実です。
独学でも短時間で合格する人もいますし、通学でなおかつ多くの勉強時間を確保しても合格できない人もいます。

私は通学で合格しましたが、勉強時間は人それぞれという印象が強いです。
しんだん+では、SNSや他の中小企業診断士の情報サイトなどを参考に、独学と通学で勉強時間に差が出るのかを徹底調査しました。
結果、優位な差は得られませんでしたが、短時間で合格した人の勉強方法にちょっとした傾向があることが判明。
本記事では、中小企業診断士試験に関して、独学と通学それぞれの勉強時間の傾向と、独学でなおかつ短時間の勉強で合格した人の体験談から、「効率の良い勉強方法」を紹介します。
これから独学で効率よく中小企業診断士の勉強を進めていきたい方は、本記事をぜひお役立てください!
中小企業診断士の合格に必要な勉強時間は約1000時間!独学の方が短い傾向だが…
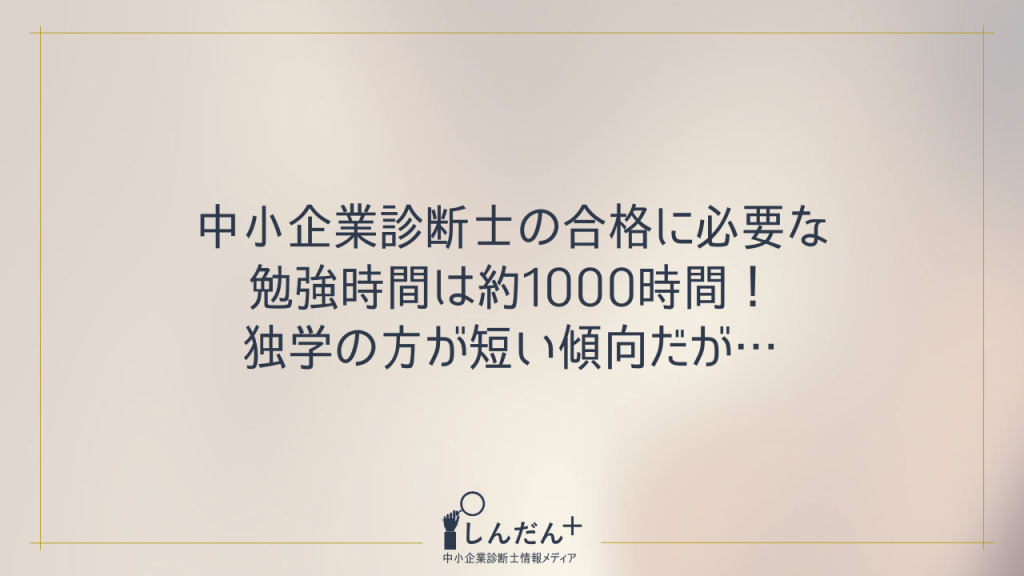
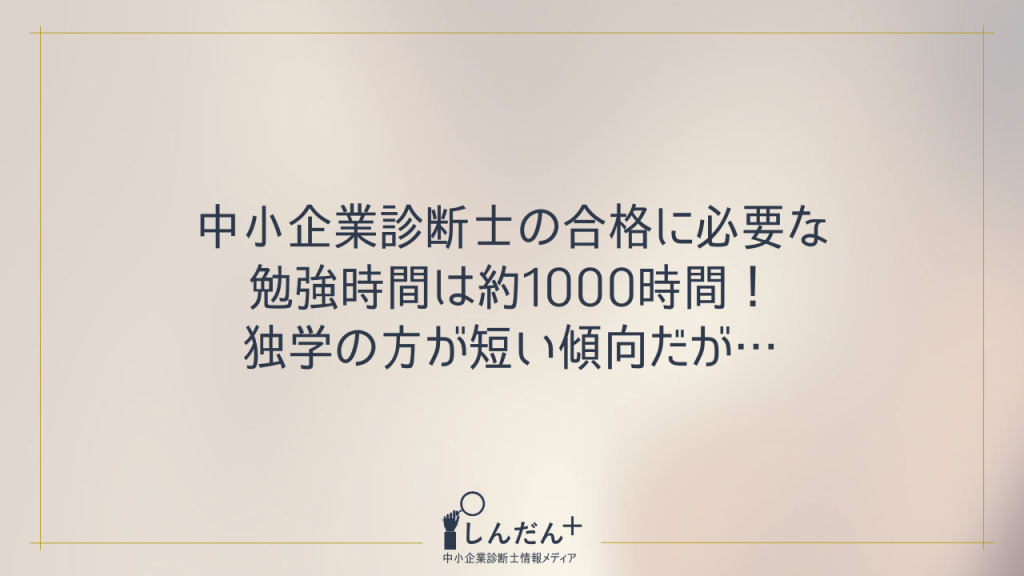
一般論ですが、中小企業診断士試験の平均勉強時間は1,000時間程度とされています。
(参考:一発合格道場「合格に必要な勉強時間は?」、TAC「中小企業診断士合格に必要な勉強時間は1,000時間!勉強法や対策を解説」)
1日2時間程度の勉強時間を確保したとしても、1年近くの勉強が必要になる計算です。
ですが、これは独学と通学関係なく計算された数字のため、独学だけで算出すると変わった結果になるでしょう。
そこで、しんだん+ではSNSや他情報サイトの勉強時間データから、独学、通信・通学の勉強時間の平均を算出。
結果は、独学の方が短いという結果になりました。
| 独学 | 通信・予備校 |
|---|---|
| 400〜700時間 | 800〜1600時間 |
ただ、通信・予備校で合格した人は、「1年目独学で挑戦したが合格できず、2年目通学で再チャレンジした」という方も多く、勉強時間が長くなってしまう傾向がありました。
ネット上では独学で勉強を2年以上続けている人のデータは見つけられず、その理由としてモチベーションが保ちにくいことが要因として考えられます。



通学で合格した私からすると、独学で400時間台というのは、
相当頭が良い方なんだなと思ってしまいます…
はっきりとした勉強時間の傾向は、個人差がありすぎて言い切れないというのが現状です。
中小企業診断士の一次試験独学合格に必要な時間は400~1,000時間
SNSや中小企業診断士の情報サイトを調査した結果、一次試験の独学合格に必要な勉強時間の目安は700~1,000時間ほどです。
中小企業診断士一次試験は、以下の7科目のマークシート式試験。
試験科目が多い上に合格基準も厳しいので、勉強時間もそれなりに確保する必要があります。
- 経済学・経済政策
- 財務・会計
- 企業経営理論
- 運営管理(オペレーション・マネジメント)
- 経営法務
- 経営情報システム
- 中小企業経営・中小企業政策
そして、中小企業診断士協会によれば、合格基準は以下のように示されています。
合格基準:総点数の60%以上であって、かつ、1科目でも満点の40%未満のないこと。
全ての科目で40%以上の点数を取らなくてはならないため、「苦手科目は捨てる」ということができません。
そのため、全ての科目を効率よく勉強していくことが必要です。
一次試験の科目別勉強時間の目安
一次試験の科目別勉強時間の目安は、以下の通りです。
| 科目 | 勉強時間の目安 |
|---|---|
| 経済学・経済政策 | 120時間 |
| 財務・会計 | 150時間 |
| 企業経営理論 | 130時間 |
| 運営管理(オペレーション・マネジメント) | 120時間 |
| 経営法務 | 110時間 |
| 経営情報システム | 110時間 |
| 中小企業経営・政策 | 60時間 |
「経済学・経済政策」「企業経営理論」「運営管理(オペレーション・マネジメント)」は、二次試験との関連性が高く、より多くの勉強時間が必要になります。
暗記が中心となる科目や、理論を理解した上で応用が必要になる科目までさまざまなので、科目の特性と自分の勉強スタイルを照らし合わせて勉強スケジュールを組むのがカギとなるでしょう。
中小企業診断士の二次試験独学合格に必要な時間は200~400時間
続いて、二次試験の独学合格に必要な勉強時間の目安は300~400時間です。
二次試験は4問構成で、企業の状況や課題に対して、それぞれ20~150文字程度で回答します。
一次試験のマークシート方式とは異なり自分の言葉でまとめる必要があるため、一次試験の内容をしっかり理解していることが重要です。
具体的な試験の設問内容に関しては、以下の通りです。
【事例1】組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例
企業の組織戦略・人事戦略がテーマとなる設問です。
過去の経営の失敗などから、組織戦略・人事戦略で施策とすべき内容などが問われています。
【事例2】マーケティング、流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例
企業の強み弱みから市場環境で生き残るために必要な取組みなどについて出題されます。
一次試験の企業経営理論や運営管理などで得た知識を活用することが問われます。
【事例3】生産、技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例
製造業がテーマとなるケースが多く、生産に関する問題点や課題解決に関する内容が出題されます。
生産計画から生産工程に至る幅広い知識を活用することが問われます。
【事例4】財務、会計を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例
財務諸表から企業の強みや弱みを分析する問題、CVP分析といった企業財務に関する内容が出題されます。
財務に関する計算力、数字をベースとした提案力などが問われます。
一次試験とは異なり、答えが明確に決まっていない試験内容となるため、二次試験は相対評価と言われています。
勉強時間の調査では、一次試験を独学で突破した方も二次試験は通信・通学に切り替えたという方も多く見られました。
二次試験の科目別勉強時間の目安
2次試験の科目ごとの勉強時間の目安は、以下の通りです。
| 科目 | 必要な勉強時間 |
|---|---|
| 事例1 | 80〜100時間 |
| 事例2 | 80〜100時間 |
| 事例3 | 80〜100時間 |
| 事例4 | 80〜100時間 |
勉強方法としては、過去問や模試を繰り返し解いていた方が多いようです。
事例1〜3は、問題文や回答のスタイルが似ていますが、事例4は財務関連の設問のため計算が必要。
出題スタイルの違いから、勉強時間を多めに確保する方も多いようです。
中小企業診断士の口述試験合格に必要な時間は4~5時間
二次試験を突破したら、最後は口述試験です。
約10分間の面接形式の試験となり、合格率も95%以上と高め。
二次試験で出題された事例に関して口頭で回答していくスタイルです。
試験中は筆記試験の問題や、実際の自分の回答を見ることができないため、自分の回答を覚えておきつつ落ち着いて回答する必要があります。
設問内容や自分の回答を覚えておく時間として、数時間の勉強時間が必要となるでしょう。
中小企業診断士試験合格の最短勉強時間は半年〜1年程度
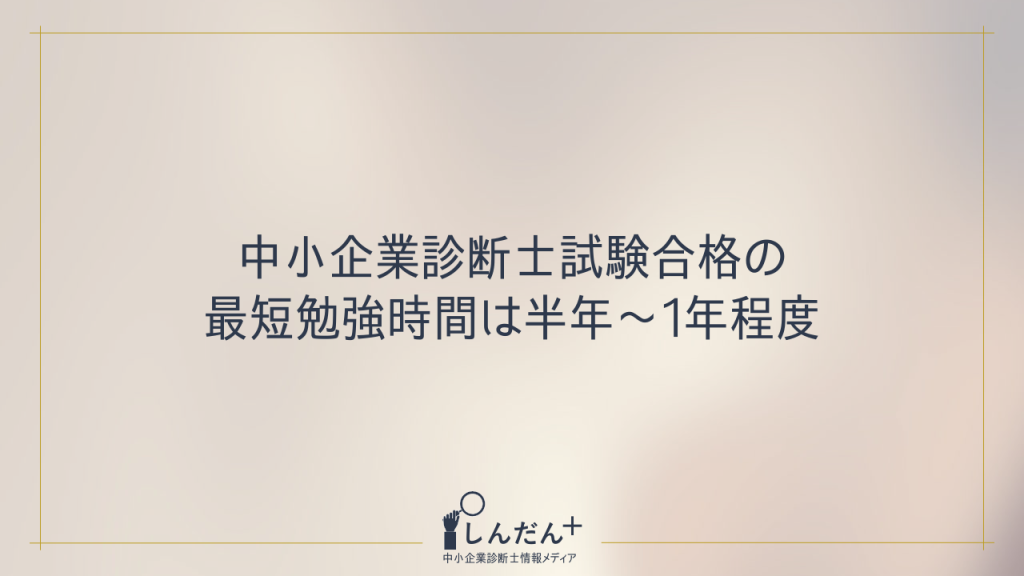
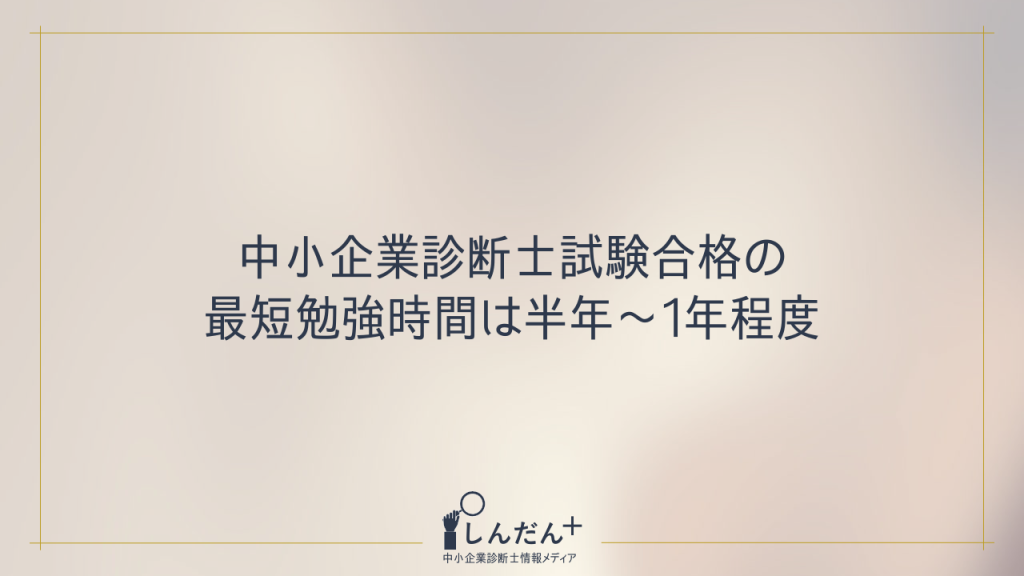
中小企業診断士の試験に合格するには、一般的に1,000時間の勉強時間が必要とされています。
しかし、なかには400時間程度の勉強時間で合格した方から通算2,000時間以上勉強したという方まで、その差は大きく開いているのが現状です。
中小企業診断士の試験スケジュールは以下のようになっており、毎年3月中旬ごろに試験日程が発表されます。
| スケジュール項目 | 時期 |
|---|---|
| 一次試験 | 8月上旬 |
| 一次試験合格発表 | 8月上旬 |
| 二次試験 | 10月下旬 |
| 二次試験合格発表 | 1月上旬 |
| 口述試験 | 1月下旬 |
| 最終合格発表 | 1月終わり〜2月初め |
独学で合格した人の中には、4月〜6月から勉強を始めたという方も多く、勉強時間は400時間程度だったという方も。
しかし、そもそも中小企業診断士の試験は難易度が高いため、全体的には1年以上の勉強時間を確保して合格した方が多い印象です。
中小企業診断士試験に独学合格するための効率的な勉強スケジュールと勉強方法
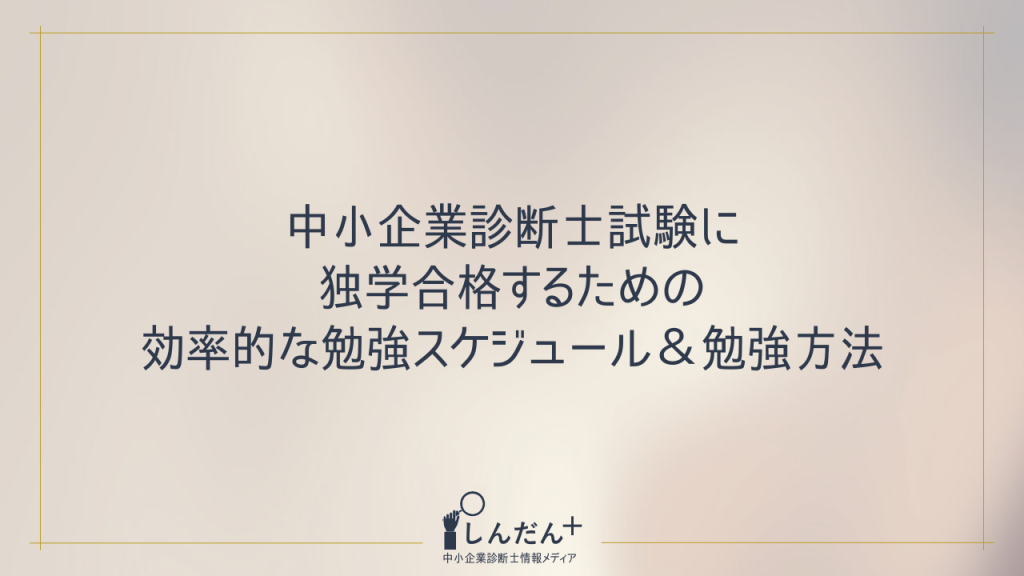
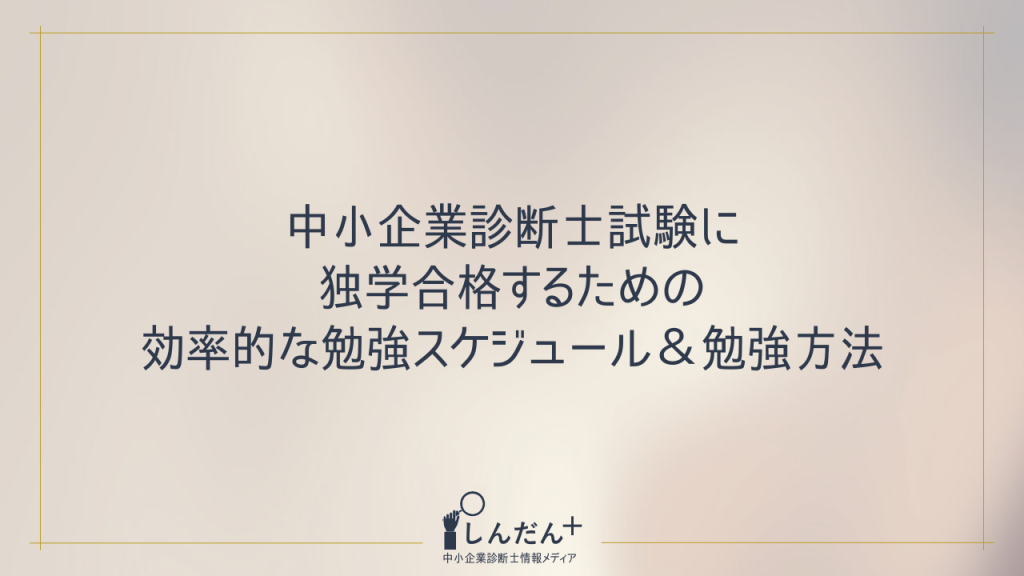
中小企業診断士の試験は難易度が高く1年以上の勉強時間を確保して挑む方が多い一方で、数ヶ月や半年といった短期間で独学で対策を進め、一発で合格している人が一定数いるのも事実です。
そういった方々の合格体験記を読み漁り、なおかつSNSで情報収集していた経験から、ここでは効率的な勉強スケジュールを紹介します。



私は通学でしたが、独学で一発合格した人の勉強法も取り入れながら勉強を進めていました!
一次試験を最短の勉強時間で突破する方法
中小企業診断士の一次試験は、マークシート形式です。
そのため、正しい知識を効率よく頭に詰め込みつつ、二次試験に向けて理解を深めていく必要があります。
その上で、短時間の勉強で一次試験を突破するために、より効率的なスケジュールはこちらです。
モチベーションが高い始めのうちに、1週目を終わらせるのが重要。
独学で試験を突破するためには、モチベーションを高く保ち続ける必要があります。
2週目は1週目に比べて格段にやりやすくなるので、「理解する」ではなく「とりあえず1週する」ことを目標に進めていきましょう。
2週目からは「この問題見たことある」という状態になるので、1週目よりも格段に進めやすくなる傾向があります。
一次試験はマーク式なので、正解の選択肢を選ぶことはもちろんですが、他の選択肢がなぜ間違っているのかも確認しながら進めましょう。
わからないところはそのままにせず、SNSで聞いてみたり情報サイトで調べたりして理解を深めていくのがおすすめです。
誰にでも苦手な問題はあるものですが、中小企業診断士の試験は合計で60点以上、全ての科目で40点以上の点数を取らなくては合格できません。
60点以上取れる科目はそこそこにして、40点以下にならないように間違えた問題だけ繰り返し解くなど、満遍なく点数が取れるような対策を行いましょう。



私ももう1回独学で挑むなら、過去問をやり込むと思います!
二次試験を最短の勉強時間で突破する方法
一次試験が絶対評価と言われているのに対し、二次試験は「相対評価」と言われます。
記述式で明確な答えが決まっていないため、独学では対策が難しいというのも事実です。
ここでは、独学で二次試験を突破するための勉強方法のポイントを紹介していきます。
論理的かつ採点者に伝わりやすい記述を研究
二次試験では、企業情報や抱える問題などが示された与件文から、指定された文字数で解答を記述します。
出題者の意図や与えられた情報から、論理的に考えた上で簡潔に記述する必要があるでしょう。
さらに、一次試験とは異なり、中小企業診断協会から明確な解答が発表されていないことも特徴です。
独学で挑む場合は、専門学校から出ている模範解答集や合格者の再現答案例などから、採点者が好む解答の傾向や記述方法を分析することが重要。
自分の考えが論理的かどうかと、伝わりやすい記述方法が鍵となる試験と言えるでしょう。
他の人よりも評価される回答とは何か?を考える
公式では、二次試験の合格基準は「総点数の60%以上かつ40%未満の科目がないこと」とされています。
しかし、毎年合格率は20%前後と動いていないことから、 相対評価になっていると考えられています。
そのため、他の受験者よりも優れた回答をすることが重要です。
論理的に考えたことが伝わる簡潔な記述や、多角的な視点が読み取れる答案を目指して、解答案を見ながら対策をしていきましょう。
中小企業診断士に独学合格するには勉強時間よりも効率的な勉強方法が重要
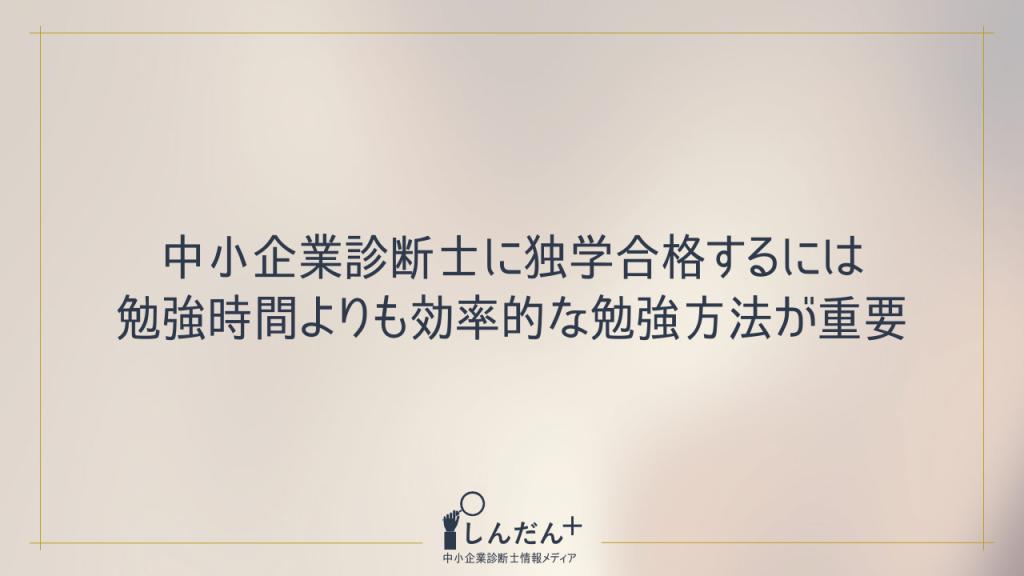
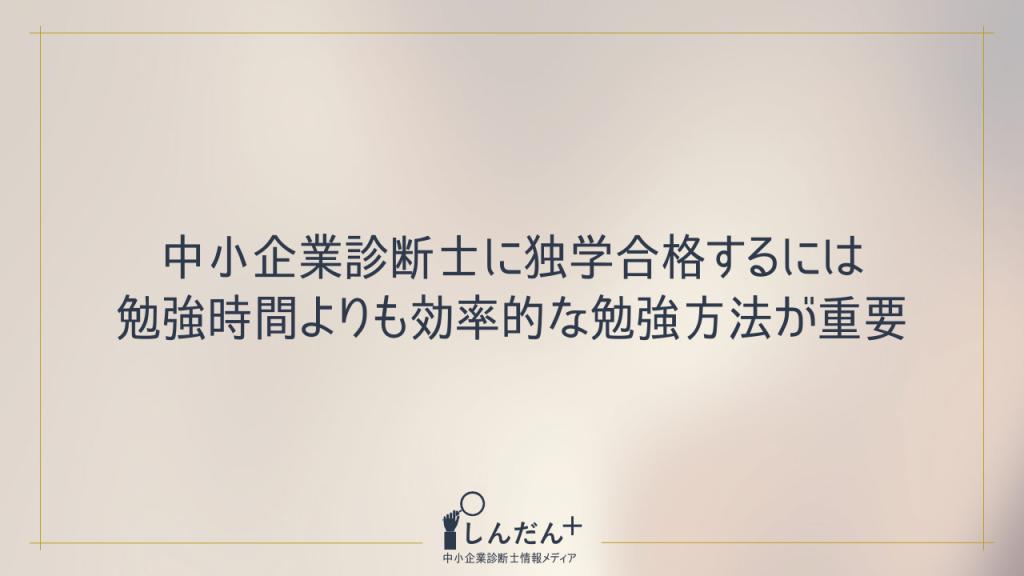
本記事では、中小企業診断士に独学で合格するための勉強時間について解説を行いました。
そもそも難易度が高い中小企業診断士ですが、独学で合格した人の方が通信・通学で合格した人に比べると勉強時間は短い傾向です。
しかし、通信・通学で合格した人の中には、「1年目は独学で挑戦したが難易度が高く、2年目に通学を経て合格した」ケースも多く、一概に独学の方が短時間の勉強時間で合格できるとは言えません。
しかし、独学でなおかつ短期間の勉強時間で合格している人がいるのも事実です。
そのような方の勉強方法を見てみると、試験の傾向を把握して効率よく勉強法を工夫している方が多い印象でした。



本当に効率の良さを求めるのであれば、通学や通信がおすすめです。
本記事が、これから独学で中小企業診断士を目指す方のお役に立てれば幸いです。




コメント